
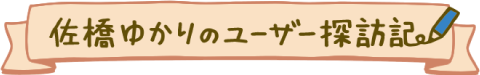
「栄養士は料理を作るだけじゃない。
私たちは保育者でありたい」
Vol.8 横浜市金沢八景保育園
USER NAME横浜市金沢八景保育園

「食事は楽しく食べるもの!だからできることをチームで実践しています」
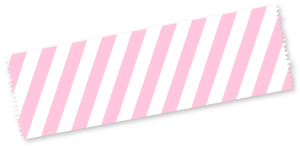

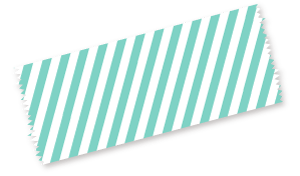

2016 年秋にリニューアルした園庭で。野菜畑があり、卒園記念樹のオリーブやレモンが植えられています。園の入り口は手入れの行き届いた草花が。
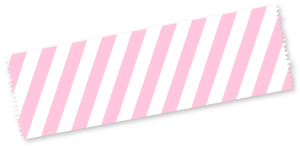

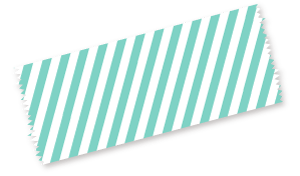

「自らが主人公になって物事に取り組める環境を整え、自主性を育てるように心がけています」と石井園長
訪問したのは…
施設名
社会福祉法人 しののめ会「横浜市金沢八景保育園」
所在地
神奈川県横浜市金沢区柳町1-3
URL
http://www.shinonome-kai.jp/hakkei/
紹介
2002年設立。60人定員規模の特徴を生かし、職員全員が子どもたちを知り、信頼関係を築き、保護者と一緒に子どもの成長を温かく支えていく、家庭的な保育を目指します。クラスは年齢の枠を超えた、0・1歳児、2歳児、3~5歳児の3つの編成。子どもたちに育ってほしいこと、感じてほしいことを、毎年テーマとして掲げていて、2017年度は「日本の達人になろう」です。
“子ども主体の保育”をかなえる心もカラダも育つ、給食を探る
保育士として働く中、「大人が決めたルールで、保育が進められていいのか」という思いを抱いたのが27歳のとき。
それから10年後の2011年から「横浜市金沢八景保育園」施設長・園長を務める石井望さんは、
子どもの未来を第一に考え、“子ども主体の保育”を理念に掲げます。いまでは全国から視察が訪れる園に成長。
“子ども主体の保育”は、食のシーンではどのようにかなえられているのでしょうか。佐橋がレポートします。
保育園は一つの社会、
職員同士の理解が大切
“子ども主体の保育”を掲げた当初は思考錯誤の連続だったと話す石井園長。「ゼロからのスタートで、手探り状態でした。しかもこの園の建物は、保育園として建てられたものではないので、使い勝手がよくありません。限られた環境で、人・モノ・空間を最大限に生かそうと考え、まずは人から。大人が楽しくないと子どもは楽しくありませんから、職員が笑顔で、主体的に動いてもらえるように。子ども同士がぶつからない静と動の空間を作り、やりたいときにやりたいことができる環境を整えました」。
石井園長が描く理想的な保育園の形とは、一つの小さな社会だといいます。「保育士、栄養士、調理師、看護師…違う職種の人たちがいる中で、ほかの職員が行っていることの大切さを知らないというのはよくありません。さまざまな立場の人たちと関わりながら、お互いを理解し合う。立場が違っても、“園児に愛情を注ぐ”という、目指している方向はみんな同じなのです」。

虫取りに夢中の子どもたち
「自分でできた! やった!」
職員は発達のサポートを
ごはん、お昼寝は何時、と時間で区切られたスケジュールはなく、遊ぶ時間、食事の時間など、おおまかに決まっているだけ。大人の指示で、子どもたちが動くことはありません。
「子どもがやりたいことをやる、というのは、自由気まま、とは意味合いが違います。子どもの意思を飲み込んで、受け止め、見守る環境を作ります。子どもの一時的な感情は、きちんと受け止めることで、落ち着きますよ」。
子どもが子どもを意識し合いながら、生活をすることを大切にしている横浜市金沢八景保育園。食事のシーンにおいても、直接的な指示はしません。「おなかが空いた子どもたちが増えてきたら、職員が食べたくなる雰囲気を作ります。食事をしたい子は、空いている席に座り、人数がそろうのを待ちます。バイキング形式の料理を自ら選んで運び、小さい子や友だちを手伝ったりしながら、楽しい食事の時間を過ごすのです」。細かく時間設定されていないからか、ゆったりとおだやかな空気に包まれています。
あくまで職員は雰囲気作りに徹し、園児の自主性を尊重。“自分でできた、やった体験”を増やすサポート役です。「もともと子どもはお手伝いが大好き。そこで大人が手を出して、口出しをすると、せっかくの気持ちがしぼんでしまいます。もちろん危ないことはさせられませんが、発達に合わせた経験は必要だと思っています」。

園庭にはたんぼも
「食育」という言葉が難しい
第一に「楽しく食べる」
「“食べる・遊ぶ・寝る”という子 かが空いたタイミングで食べることが心の満足度につながります。ごはんを食べて、おかずを食べて、口の中でもぐもぐして、みそ汁で口をリセットする。手づかみ食べ、三角食べ、はじめは、ばっかり食べでもいいのです」。
使命感を取り払った
食べたくなる雰囲気作りとは
食事の時間までは準備で大忙し。栄養士、保育士の表情が険しくなり、これから大変なことがはじまる…といった雰囲気になっていませんか? その原因は「決まった時間に、決まった内容を、きちんと食べさせなくてはならないという使命感が、大人にあるからなのでは」と石井園長。子どもが給食をひっくり返し、0・1歳児はこぼすこともあります。そこは口出しせずに受け止め、楽しそうな雰囲気を作るのが何より大事なのだそう。
そこで大切になってくるのが、職員の連携です。石井園長から栄養士へ伝えているのが、「食事の時間、子どもがどのように食べているのか、どんな箸の使い方をして、食器は合っているのか。しっかり見て、感じてほしい。料理を作る人の枠を超えて、保育園という社会の一員になってほしい」。栄養士は必ず1人が食事の時間に立ち合い、保育士と連携して、給食を充実させています。


いただきます!
主体性には個人差が
無理強いせずに経験を
保育者は子どもたちに、好き嫌いなく食べてもらいたい、マナーを知ってもらいたい、箸の使い方、お椀の持ち方、三角食べも覚えてもらいたい…とさまざまなことを願います。
園での取り組みを通して、自分で考えながら食べられるようになる子もいれば、ならない子もいるとのこと。
「保育園で伝えてないわけではありません。それは子ども次第で、無理強いはしません。応えてくれる子もいるし、いまはそこで止まって、もう少し先になるという子もいます。子どもがどういう風に経験して、どうしなきゃいけないのか感じてもらうことが幼児教育で、できるようにさせることではないと思っています。自分でできた、自分がやった、という経験をもっともっとさせたいですね」と石井園長は話します。

スプーンを洗う子の横には、すでに終わって歯を磨く子が
食べたくなる雰囲気作りの例
- 「先生は、おなかが空いちゃった」「いい匂いがするね」と、園児と会話します。
- 「今日のお魚は甘いのかな、しょっぱいのかな、どんな味かな」など、独り言のように話し、食事への興味を誘います。
- エプロンを楽しそうにつけるなどして、楽しい食事がはじまることを動作で表現します。

まだできないことは自然にフォローします
栄養士は配膳に入りモニタリング
「さあ!食事の時間です」
給食では実際、どのように自主性を大事にしているのでしょう? この日は園庭でプール遊びや虫取りに夢中の子どもたち。なかなか食事がはじまりませんでしたが、先生たちはニコニコと見守ります。栄養士は配膳に入り、子どもの栄養状態をモニタリングします。
-
1子どもたちはおなかが空いたら、空いているテーブルに座り、自分でランチョンマットを敷きます。テーブルは5~6人がけ。人数がそろい、自分たちの名前が呼ばれるまで、子どもたちは座って待ちます。

【ポイント】
自分で用意するランチョンマット。食べたい合図です
-
2自分の名前が呼ばれたら、イスをしまって、それぞれが給食を取りに行きます。「いっぱい」「少し」「いる」「いらない」など伝え、トレーに食べたい料理、分量を盛り付けてもらいます。

【ポイント】
子どもが選ばない料理があったとき、栄養士は「あまり好きじゃない?」「どんな味付けがいい?」と話しかけます
-
3トレーを席まで運び、みんなで「いただきます」。おかわりをしたい場合は、食べた皿を再度持っていき、どのくらい食べたいかを伝えます。食後は年長児が中心となって食器を洗い、それを他児が見て、一緒に真似ています。

【ポイント】
机にトレーを上手にかけて並べる姿が。ごはんは左側…など皿を並べる位置も自然と覚えていきます
栄養士さんにインタビュー
「子どもの成長を願う、前向きな環境。栄養士としてアイデアが膨らみます」
「自分ができた、やった経験をもっともっとさせたい」。石井園長の方針のもと、子どもに主体的に食べてもらうために、保育士は声がけや、雰囲気作りを行います。一方栄養士は、園児に選ばれる給食を作るため、より思いが強くなるのでは? 工夫や心がけを、栄養士の丸山奈津美さんに聞きました。(以下敬称略)

栄養士 石井望さんと園児のみなさん

栄養士 丸山奈津美さんと
食べてもらうために、どんな工夫をしていますか?
丸山
まず見た目です。工夫できていないと、子どもたちに「いらない」といわれてしまいます。食事の時間、子どもたちを実際に見ているので、直接意見が分かりますし、残食を見ただけでも、「彩りが悪かったかな」と思いますね。ほかには、子どもたち自ら調理する「クッキング」を積極的に取り入れています。例えば、「トマトのマリネ」のメニューがあると、保育士と相談して「園庭のキュウリを入れてみようか」と。その日は、子どもたちが自ら野菜を収穫し食べる分を作ります。すると食べ方がまるで違うんです。
クッキングは計画的に行いますか?
丸山
当日に、「今日、園庭の野菜が食べたい」と保育士から相談を受けることもあります。「いまから園庭でやりたい。包丁とまな板を貸してほしい」と。それはおまかせして、必要なものと材料を渡します。月ごとには、食育の一環として、計画してやっています。大がかりなのは、年間の後半に。3~5歳児クラスが、その日のメニュー(汁もの、主菜1品、副菜2品)を全部自分たちで、全員分を作るんです。達成感もすごいと思います(笑)。
急なクッキングで園庭の野菜を使う場合、時間管理や料理の調整はどうしていますか。
丸山
急な場合はクラスが主になって対応しています。時間はクラスにお任せして、喫食時間内に食べてもらいます。園庭で収穫した野菜、例えばトマトやキュウリの夏野菜など、そのまま食べられる野菜に関しては塩をふって食べています。加熱して食べる野菜は献立に反映するか、夏野菜を収穫してラタトゥイユを作ったり、枝豆を茹でるなどのクッキングを行っています。クッキングする時は、大量ではないので、昼食を減らすなどはしていません。
楽しさを大事にしているという点で、行事食も取り入れていますか?
丸山
はい。五月の子どもの日に作った「ちまき」は大好評でしたね。竹皮に包まれていると、子どもたちは食べ物じゃないと思ったみたいです。開けてみるとごはんでびっくり! 嬉しそうによく食べていました。
日本の食文化を栄養士として伝えたい、という思いもあるのでは?
丸山
保育園で決めている年間テーマがあり、今年は「日本の達人になろう」です。テーマに沿った郷土料理も扱っていきたいですね。昨年実感したのですが、「クッキング」スタイルだと、子どもたちはより馴染めるということが分かりました。
今日は、バースデー会もしていましたね。
丸山
私たち栄養士が心がけていることは「料理を作るだけが仕事じゃない」ということ。できるだけ保育士と同じように、保育者でありたいねと。私たち栄養士から子どもたちに、何かお祝いができないかな、とバースデー会をはじめました。誕生日を迎える園児に、カルピスゼリー、パフェ、ホットケーキの3つの中から、そして好きな旬の果物を選んでもらう。食べる時間も選んでもらいます。ごはんの前…といわれることもあります(笑)。希望に合わせて、楽しんでもらいます。おやつとともに職員たちからのメッセージカードも贈ります。
バイキング形式だと、子どもが一度に取りすぎて、残食が出ませんか? 献立作りやコスト管理はどうしていますか?
丸山
やっぱり残食は出てしまいますが、あらかじめ多めの量を想定して作っていて、欠席分はおかわり分に回しています。献立は栄養士3人で立て、担当月以外の栄養士が、内容に漏れがないかをチェックします。食材の発注は旬を意識し、すべてその日のうちに使用していますね。野菜が高騰すると安い食材で対応し、乾物やお米などは子どもの人数が少ないときに、減らすなどしています。
栄養士としての今後の目標を教えてください。
丸山
給食の時間に立ち合い、成長が目の前で見られるのは喜びです。昨年から配膳に入るようになったのも大きいですね。これからは、地域との共存、地域活動に力を入れたいです。保護者への発信は以前よりできるようになったので、地域の方々を園によぶなどして、地域交流を頑張っていきたいです。また、地元の農園に月1回子どもたちと見学しています。この農園活動を、食育につなげていきたいですね。

行動食の例
【子供の日のメニュー】
- ちまき
炊けたごはんを、笹の葉に詰めて昼食に提供。「笹の葉の匂いを嗅いだり、もちもちしたもち米の食感を味わったりと日本の行事食に触れあうことができました。1つずつ手作りするのは大変ですが、子どもたちの嬉しそうに食べている姿を見ると、作ってよかった、また来年も頑張るぞと心から思います」と丸山さん。子どもたちへの愛情がたっぷり詰まったメニューです。

【クリスマスメニュー】
- えびとチキンのドリア
- かぼちゃのサラダ
- コーンスープ
- いちごサンタ
クリスマスパーティーは午前中から。「締めくくりとして食べるメニューなので、毎年特別感を出せるように力を入れています。セミバイキング形式で提供し、昨年はお皿からはみ出るくらいのドリアを嬉しそうに食べている子も。いちごに生クリームを挟んでクリスマスらしさを出し、子どもたちは大喜びでした。かぼちゃのサラダは、コンソメで煮て味をつけたものをマッシュし、胡桃とレーズン入りです」。食の演出でパーティーがさらに盛り上がる様子が目に浮かびます。

RECIPE
メロンパン風クッキー


材料(32人分)
- ホットケーキミックス200g
- 卵1個
- 砂糖15g
- グラニュー糖10g
- サラダ油40cc
- バニラエッセンス2g
作り方
- ホットケーキミックスに、砂糖を混ぜる。溶き卵・サラダ油・バニラエッセンスを加え、粉っぽさがなくなるまで混ぜる。
- 生地を32等分にし、丸める。
- ナイフでメロンパンのような切れ目を入れ、グラニュー糖をふりかける。
- 180℃に予熱していたオーブンで、7~8分焼いたらできあがり。
※少し大きめに作ると、ふわふわのメロンパン風になります。
※生地が硬い場合は、牛乳で調節できます。
※ホットケーキミックスを使用しているため、できあがりが膨らみます。切れ目はしっかりと付けると良いです。
すいかのフルーツポンチ


大きなすいか1個分
- カルピス670g
- パイナップル缶400g
- 水2700g
- みかん缶400g
- 粉寒天30g
- すいか5~6kg位
作り方
- カルピス・水・寒天を鍋に煮溶かし、バットに流す。冷やし固めて、サイコロ状に切る。
- パイナップル缶は、1/10切りにする。
- 肉に塩を加えてよく練り混ぜる。
- すいかの上部1/3くらいをギザギザに切り、器にする。すいかの中身をスプーンで取り出し、種を取り、一口大の大きさにする。
- (1)、(2)、みかん缶、すいかを混ぜ合わせ、すいかの容器に入れたら完成。
※すいかから出た果汁を一緒に混ぜると、配膳もしやすく、甘くておいしいです。
※夏バテしがちな季節にぴったりで、子どもたちもとても良く食べてくれるおやつです。
NOTE編集後記
わたしたちは、子どもたちに愛を持ってソフトを作っています。携わるスタッフには、「栄養士の先生は、ソフトを使う人じゃなく、子どもたちに愛を注いで食事を作っている人たち。だからいかに簡潔に、分かりやすく説明するのかが大事で、それが子どもの幸せにつながっているんだよ」と話しています。給食ソフト「わんぱくランチ」が、その一端に関われているというのは、幸せなことです。保育園を訪問すると、モチベーションがあがり、自分たちがやっている仕事の意義をすごく感じられるのです。
横浜市金沢八景保育園のみなさまは、熱い理念をしっかりと具現化され、何より先生と子どもたちの笑顔が印象的でした。これからのユーザー訪問も、ぜひお楽しみに。素敵な園の取り組みを紹介していきます。



























 資料請求
資料請求 お問合せ
お問合せ












