
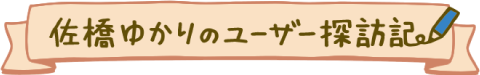
母の想いが生んだ24時間丸ごと保育
みんなで紡ぐ子供の未来
Vol.19 ぽっぽのいえほいくえん
USER NAMEぽっぽのいえほいくえん

訪問したのは…
施設名
ぽっぽのいえほいくえん
所在地
東京都新宿区下落合1-16-7
URL
https://www.taiten-hoikuen.com/
今から59年前、女性の労働力が必要になり、保育所を必要とする声が高まっていく中で、ポッポの家共同保育所が創立されました。対象は0~2歳児、定員は15名でした。そして社会状況、社会制度の変化に伴い保育室から認証保育所に移行したのが2011年3月、現在のぽっぽのいえほいくえんです。定員は40名、現在は0歳児4名、1歳児10名、2歳児以上25名が共に生活しています。周辺には公園が数多くあり、川が見下ろせる3階建ての当園。共同保育所のコンセプト(二回食制・野菜中心の食事・布おむつ使用)を引き継ぎ、子供の情緒の安定や言葉の発達を育んでいます。
保育目標
- 心身ともに健康なこども
- 友だちといることを喜ぶこども
- 自主性のあるこども
- 考えることができ、良いこと悪いことが判断できるこども
みんなでつくる楽しいほいくえんに
- こどもたちの声が響き、笑顔が輝く保育を
- 安心で安全な食材を選び、たのしい給食つくりを
- 保護者と保育者、理事がお互いの役割分担をしながら、あたたかい心の通い合う保育園づくりを
60年前の保護者の思いをそのままに
「出発点は子供の様子を見て」「丸ごと24時間の生活をどう私たちが捉えてそれをどう保障していくか」そう話すのは理事長の馬渕磯子先生。当園のコンセプトの土台となる共同保育所を設立された第一人者です。時代と共に変化する社会の風潮、大人にとっての当たり前が一般的な考えになりがちな世の中で、常に子供の視点で作り続けてきた保育がありました。「社会に反発があった。大変だけど逆にすごいおもしろかった」。自分たちで作り出すことに意義を感じ、継続して取り組むことに誇りをもっている先生方のバイタリティ溢れる実践例をご紹介します。
子供の視点で理解する先に生まれた
革新的な食事のリズム
当園の一番の魅力は「二回食制」です。おやつの時間はなく、11時と15時に野菜中心の食事を摂ります。
二回食制が生まれるきっかけは、遡ること59年前、理事長が共同保育所を設立された時代にあります。「産休明けや0歳児保育は、50年前はあまりなかった。乳児は家庭で見なさい、という風潮があった。自分たちで(保育の場を)作り出すしかしょうがなかった、というのが始まり。東京都や全国に連絡会を作って、みんなで研究してきた」と振り返ります。設立当初、現場を通して最初に感じた課題は生活リズムでした。手探りの中で始めた保育、食事に関する知識も乏しく「(食事の時間は)分からないから10時と14時に決めていた」のです。ところが10時の食事が始まると眠気を見せる子供の姿がありました。理由は「生活リズムがバラバラ」であることでした。「この眠い時にご飯をあげちゃだめ」と問題意識を持ちました。課題解決のために、研修会に足を運び、情報交換を行う中で「子供の食事に適した時間は、眠って起きて一番気持ちが良い時だ」、子供が元気な状態で食事に向かうために「生活リズムを整える必要がある」という考えに至ったのです。「0歳児の生活リズムは、食べて・遊んで・寝る、の繰り返しが大事」という学びも後ろ盾になり、「生活リズムを整える」を基盤にした保育の実践を加速させました。具体的な改善点として、「小さい子は大体ミルクしか飲んでこないから早めにおなかがすく。10時半頃を目途に毎日食べさせようとなった。そのために午前中はしっかり寝かせる。食べて、寝て起きてから、お散歩に行って帰ってきて、それで睡眠に入ろうということになった。そうなると(次の食事は)4時間程空けるから14時半頃になっていく」と教えてくださいました。

二回食制が始まるきっかけには、働く保護者が子供の健康を気づかう思いから生まれたという一面もあります。理事長は言います。「帰宅が夜遅くて子供達がおなかをすかせているため、どうしてもお菓子を食べさせる。そうしたら夕飯を食べなかった、になる。それじゃあ、まずい」と問題意識を持ったのです。それから「夜食事ができるように、お菓子じゃないものをちゃんと食べさせてあげよう」と考え、改善策として「夕食までもつような食事にしたら4時間空いても良いんじゃないか。15時頃に食事時間を設ければ、帰宅後ご飯の用意ができる19時頃にしっかり食べられるよねっていう設定にしていった」のです。このように、食事の様子を通して、子供の生活リズムの面と健康面に課題意識を持ち、行動し続けた結果、二回食制が生まれたのです。
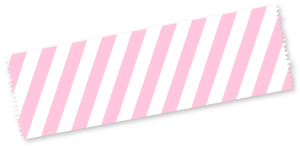

当園の保育を牽引されている馬渕理事長。
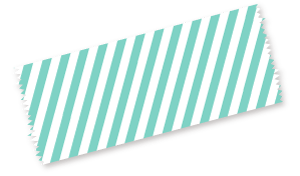

現在は、週に一度子供達と顔を合わせて、現場を見守っています。
「大変」を越えられるのは、
繋がる想いがあるから
子供にとって理想的である一方、二回食制に携わる大人にとっては様々な手間や労力を要することが想像できます。そこで、調理師の遠藤智香子先生にお話を伺いました。基本的に2人体制で調理をしています。スケジュールは、8時半に午前食の仕込みを開始、10時半から配膳、11時15分に器具洗浄、一旦休憩を取ります。その後、午前食分の食器洗浄(午前食に使った食器を午後食で使用するため)と同時進行で、午後食の調理を行います。調理作業の観点からいうと、楽に野菜を使いきりたい気持ちや、検品作業の負担を軽減させたい気持ちから、二回食で同じ材料を使いたくなりそうなところです。ところが、遠藤先生は子供達への配慮を優先して、午前食と午後食に使う材料は「なるべくかぶらないように」しているのです。子供達に新鮮で旬の食材を届けるために、自ら八百屋に出向いて1日に使い切れる量の交渉をしています。調理員として働き続ける想いを尋ねると「絶対働きたいと思った」と当園のコンセプトに賛同した想いを語ってくれました。「好きなことを仕事にできた。苦にもならない」、それから「子供達の笑顔」が原動力になると教えてくださいました。
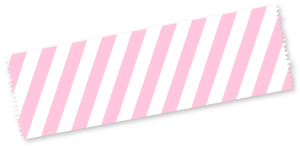

厨房で左から、調理員の星野美紀子先生・川村園長・遠藤調理師
.
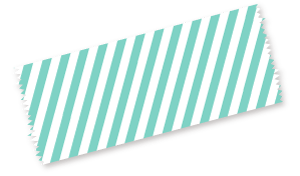

当園の食事のこだわりを語る川村園長。
子供達からは「かぁーか」の愛称で親しまれています
園長であり、長く保育士としてご活躍されている川村克子先生は、元々はご自身のお子さん4人を当園に預けていた保護者でもあります。保育士の視点のみならず、保護者としての実感を得ているからこその力強い口調で「ぽっぽの一番の魅力は食事」「(育児の中で)食事に関して悩んだことがない」と語ります。一方で二回食制を継続することについて「厳しい、難しい」ともおっしゃいます。例えば「15時に食事を摂ることで、帰宅後にご飯を食べない」という悩みは毎年数件聞かれるそうです。「保育園で1日に必要なkcal数の半分以上は稼いでいるので、主食は抜かしておかずだけ食べる」「時間があれば帰りに遊んで帰る」などの助言をしています。
二回食制を実現させるためには家庭との連携も欠かせません。なぜなら、11時にしっかり給食を食べるとなると「朝食を7時頃までには摂っておけると良い」「朝食に合わせて睡眠時間を設定できると良い」からです。これらのことを「常日頃口酸っぱく(保護者に)言っている」そうです。とはいうものの、「食べること」と「生活リズムを整えること」を繋げて考えることは実感が伴わないと、なかなか難しいのだと言います。保護者にモチベーションをもっていただく工夫として、保護者同士の交流を大事にしています。例えば、年に2回程行われるクラス懇談会では、降園後の生活リズムをテーマに、悩みなどを共有・共感する時間を設けています。また、就学前まで連絡帳を介して食事の確認やアドバイスを行っています。
このように、二回食制に携わる大人達が同じ目標(子供が元気に食事に向かえる姿勢、子供にとって健康的な食事習慣の形成)に向かって手を取り合いながら、それぞれの役割を果たしているのです。例え大人にとっては大変な作業であり困難だとしても乗り越えられたのは、コンセプトに賛同する熱い想いがあるからです。その熱い想いの背景には子供への愛情だけではなく、一人一人の経験から得た知識だけでもなく、子供を取り巻く環境や社会に対する疑問や反発心もあったのでしょう。理事長は「作り出す意義があった」とおっしゃいます。ただ「子供が健康になること」だけに意義を感じているのではなく、「子供に対する大人の想いが形になっていくこと」「想いが繋がっていくこと」に意義を感じられているように思うのです。
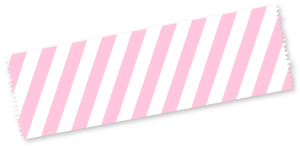

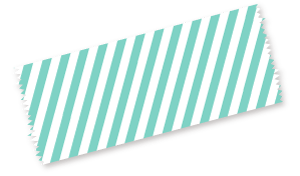

良いこと尽くし!情緒の安定と誤飲予防
様々な人の想いをのせて続いている二回食制は、子供の情緒の安定を図る効果があります。理事長は「(子供が)朝の時間も元気になって機嫌が良くなるし全部が良くなる」、園長は「保護者にとっても結局は楽。子供が食べない、朝起きないということもない」と話します。
さらに、二回食制は誤飲予防の効果もあります。当園は、午前食に果物は出しません。なぜなら子供が眠くなりやすい時間帯だからです。午睡後、午後食に生の果物を提供しています。理事長は誤飲の防止策について「刻みにするとかすりおろすという思考になりやすいが、違うと思う。生活リズムが悪い。子供が咀嚼できるくらいの薄さで切っているはずだから、子供が元気なら食べられるはず」と訴えます。
「子供が元気に食事に向かえる姿勢」や「子供にとって健康的な食事習慣」を獲得するために必要な保育を、24時間、または1週間単位といった大きな枠で捉えること、生活リズムという視点で大人が捉えて実践することができれば、情緒の安定や誤飲の予防にも繋がるのです。
二回食制を支える食事の工夫
栄養に配慮した健康的な側面と食文化を生かす文化的な側面があります
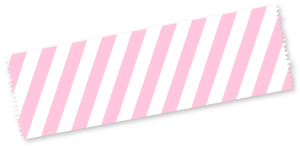

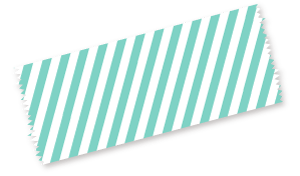

① 野菜中心
園長は「日本食の良さは野菜や出汁のうま味。伝統的なものをそのままに、日本食の良いところを出していければ、と思う」と話します。「昔からの当園のやり方で、シンプルに味付けしている」と遠藤先生が話されるとおり、訪問当日の副菜メニュー「チンゲン菜としらすの和え」に使われている調味料は醤油のみ。実際に試食をさせていただき、驚きました!使われている調味料が少ないことにより、野菜特有の苦みやえぐみがないのです。「シラスは調味料を少なめにしているので塩抜きはしていない」とのこと、素材のうま味や塩分が味わえます。大根や人参は細く千切りにすることで甘みが出やすくなっており、さらにシラスのわずかな塩分との相乗効果で野菜の甘みが引き出されます。食感についても、チンゲン菜の程よいシャキシャキ感、大根の柔らかさが絶妙です。料理に合わせて、一つ一つの素材の茹で加減が徹底されています。和え物は、一つの鍋で茹でているのだそう。「チンゲン菜としらすの和え」は、ニンジン、大根、最後にチンゲン菜の順に茹でるのがコツです。人参、大根の甘みが含まれたゆで汁を使ってチンゲン菜を茹でるため、チンゲン菜が甘く感じられるのです。こうした調理員さんの数々の工夫によって、料理に一体感が生まれていました。子供は異なる食感や味、素材を同時に口に入れることを敬遠しがちです。そういう要素が含まれている「チンゲン菜としらすの和え」に一体感を持たせ、子供が口にしやすい料理に仕上げることは簡単なことではないはずです。「3歳以降は野菜に対して何も言わなくても食べちゃう」と園長が言う通り、おいしそうに「チンゲン菜としらすの和え」を食べる子供達の姿が見られました。一方で「離乳期や1、2歳児は食に関して色々出てくる時期で大変であり、大事な時期」だと言います。給食が始まると、子供たちが食べるきっかけを作るための保育士さんの働きかけが見られました。1歳児さんのクラスではこんな場面がありました。大きな口を開けて食べるお友達を指さし「ライオン」と教えてくれるお子さん。すかさず保育士さんが「ライオンのおくちだね」「〇〇ちゃんは誰のおくちにする?」、聞かれたお子さんは「コアラ!」と言いながらごはんをぱくり。2歳児さんのクラスでは、「チンゲン菜としらすの和え」になかなか手が伸びないお子さんがいました。保育士さんやアドムのスタッフに褒められているお友達を真似して、匂いをかぎなから恐る恐る一口。保育士さんとお友達も一緒に手を叩いて喜びます。さらにもう一口!最終的に、「チンゲン菜としらすの和え」を飲み込むことはできませんでしたが、風味や舌ざわりを経験できたのではないでしょうか。このように、どのクラスにおいても一人一人のお子さんの発達や興味、関心に合わせた働きかけがされています。
そして、調理員さんと保育士さんの連携の賜物でしょう、なんと残菜がほとんどないそうです。遠藤先生は「びっくりした」ととても嬉しそう。それから「好き嫌いやその日の気分で食べない子もいるが先生達の声掛けの工夫もある」と教えてくれました。園長は共に働く保育士さん達について「一番短い先生が6年目。職員がみんな長く働いているから言いやすい環境」「知識が共有できている。勉強した先生たちがやめないでいてくれることも強みになっている」と教えてくれました。調理員さんの経験から生まれる知識と、保育士さんの遊び心ある子供達への働きかけの工夫が連携することにより野菜中心の食事が支えられているのです。
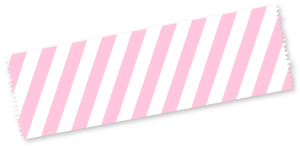

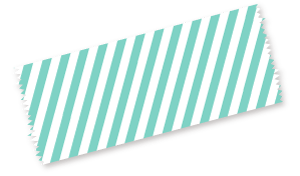

② 砂糖を使わない
園長は「砂糖は常習性がある。薄味で野菜の味を楽しめることができたら、大人になっても砂糖のお菓子の常習性は生まれないんじゃないかと思っている。乳幼児期にしっかりとした味覚を確立し卒園してもらうのが目標」と話します。当園では「ホットケーキミックスを使っているのでそれに砂糖が入っているくらい」だそうで、甘い味覚は、人参やカボチャなどの野菜で教えていきます。このように、砂糖を使わないという制約を自分達に課すからこその工夫が必要になってくるはずです。
調理面では、野菜の青臭さを少量の砂糖を入れることで消すことができますが、それに代わる工夫については「野菜(人参、玉ねぎ、えのき、コーンなど)の甘みを使う。野菜の煮汁を味噌汁に使う」と教えてくださいました。
栄養面では、「砂糖を使わない分エネルギーが上がらない」悩みがあるといいます。そこで、アドムより解決の糸口として、2点ご紹介させていただきました。1つ目は、当園が大切にされている「生活リズムを整える」にあります。家庭と連携して1日のリズムの中でしっかり食べさせていくということです。お子さんの胃の大きさを考えた時に一度にたくさん食べるというのは無理があります。野菜やご飯を食べて、たんぱく質を摂って、砂糖は使わないとなると、起きる→朝食をしっかり食べる→元気な状態で登園→遊ぶ→食べる→寝る→食べる…のリズムを整えることが必要不可欠なのです。元気に登園してくるからこそ遊べる、食べられる、寝られる…ということです。
エネルギーを上げるための解決策の2つ目は「質の良い油を上手に使う」ことです。海外では、離乳食の段階から良い油を使っています。油を中に仕込ませていくことが一般的なのです。例えば、魚を焼く時に使用します。良い油を使うとうま味が閉じこもります。塩や砂糖に頼らなくても中身がふっくらし、外でコーティングされるのでおいしく食べることができます。また1g程度の油を魚に仕込ませることで、お子さんの噛みだめがなくなって食べやすくなる効果もあります。また、油と合わせて片栗粉を一緒に使うことでエネルギーが約20kcal上がります。質の良い油を上手に使うことが、エネルギーを補完すること、そしてお子さんにとっての食べやすさに繋がるのです。
先生方が様々な悩みに直面しながら続けている「砂糖を使わない給食」。それを経験したお子さんの保護者は、保育園以外の場所での食事に関する認識が変わるそうです。「卒園後に保護者から、学童の食事がお菓子になる。どうしよう。と相談されることがある」と園長は話します。保護者自身がわが子の食事を選択する時に、当園での経験や先生方の言葉を通して、子供にとってより健康的な食事を選択できるようになるのでしょう。また、当園の健康的な食習慣が身に付いている子供には、保護者の選択を受け入れる土台が出来上がっているのでしょう。そんな未来のための基盤がここにあると感じました。「砂糖を使わない」その思いは、子供達の現在だけを見るのではなく、未来を見据えているからこそ生まれたものなのです。
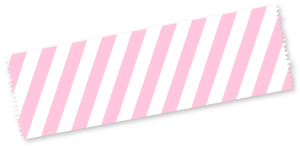

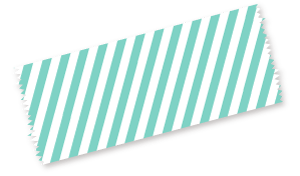

③ イベント食
様々な旬の野菜が使われた素朴な食事と、子供達が喜ぶイベント食のメリハリが魅力的な当園。いかに食を中心に保育が行われているかが分かります。
・ライスケーキ
月に1回行われるお誕生日会で提供されます。その月をモチーフにした可愛らしいデザインが目を引きます。様々な種類の野菜が薄く模られて飾り付けされた料理からは先生方の地道な作業が伺えます。子供達は一目散に見に来るほど楽しみにしているそうです。

・郷土料理
こちらも月に1回提供されます。発案者の遠藤先生は「郷土料理は日本の良いところを集めたものが多くて、ぽっぽに合うと思った」と話します。地場の野菜を中心とした郷土料理が食べられるということは、子供達が野菜を食べ慣れている証拠です。日々どれだけ健康的な食事を提供しているかが分かります。

・イベント食として提供するいとこ煮
華やかな料理の背景には、子供達の食経験の変化に対応する調理員さんの努力があります。
当園で7年程調理されている遠藤先生は「年に1回になってしまった献立も結構ある」「今の子は食品があふれているので食べなくなってきている」と話します。かつての定番メニューだったいとこ煮もその1つです。「昔はみんな食べていたが最近は苦手になってきている」と言いますが、だからと言って提供をやめるわけではありません。素材としては提供するのです。つまり、かぼちゃはチーズ焼きに、小豆はおしるこに、といった具合です。目の前にいる子供に合わせて、食材を組み合わせて別の料理に変えているのです。そして、いとこ煮は、イベント食として冬至の月にだけ提供しています。「イベント食」にすることで特別感を演出し、料理に意味を持たせるのです。子供達が食べてみたいと思うきっかけ作りになっていることでしょう。
 様々な工夫が凝らされた料理の写真はSNSで見ることができます
様々な工夫が凝らされた料理の写真はSNSで見ることができます
今までも、これからも、みんなで作る
今回は、食事の様子を通して見つけた課題である「生活リズムを整える」と「健康的な食習慣を獲得する」を達成するために、実践されている工夫をご紹介させていただきました。そして、課題を洗い出す過程でヒントになったのは「丸ごと24時間の生活をどう私たちが捉えてそれをどう保障していくか」という視点でした。
これまで伺ってきたお話を通して、先生方を例えるならば、子供の代弁者であり、保護者の応援団です。応援団と言っても、ただノウハウだけを伝えて背中を押すのではありません。先生方の魅力は「お母さん達の分からない気持ちに気付ける」ところにあります。例えば、理事長は「(保護者に)中身を教える」と言います。保育の手段だけではなく、目的や意味を子供の視点で伝えるのです。このようにお母さんの気持ちに気付ける心が根付いているのは、母体となる共同保育所を運営する保育者が当事者であったからではないでしょうか。子をもつ母親が自分達に必要な保育を自分達の手で作ってきたから、保護者の気持ちに気付くことができるのです。理事長は「補助金はないし保育者への給料も払えない」状況で、子供を最優先に「お母さんと一緒に勉強しながら食べさせてきた」と話します。当時の経験や想いが褪せることなく、これからの保育を作る先生方に引き継がれています。だから、先生方は単なる応援団ではなく、並走者として保護者の気持ちに寄り添うことができるのです。
保護者の応援団であり並走者である先生方は、子供にとっては代弁者です。理事長は、全ての始まりは「子供の様子を見て」と言います。現代は、保育や食育に関する指針が定められており、実践集は潤っており、我々にとって心強い味方が山ほどあります。ともすると、そこに示されたことだけが正解だと錯覚します。対象の子供を決められた枠に当てはめて考えることは、保育者自身の視点を狭める可能性があります。子供にとって本当に必要な保育が見えにくくなるのです。一方で当園は、道しるべがない時代から、ないからこそ、目の前にいる子供の声を聞くことに徹していました。代弁者として、枠にとらわれることなく、その子にとって必要なことを観察し、理解し、形にしてきました。そうすることの意味や効果は、60年の歴史が、実績が、物語っています。「自分達で作り出す意義があるから保育者が生き生きしていた」という言葉からも感じ取ることができます。食事に関わる大人たちは、子供の生活全体に、子供と生活する保護者に、子供の未来に、貢献できる可能性があるのです。


























 資料請求
資料請求












